情報処理技術者試験の論文試験を苦手とされている方は多いのではないでしょうか。
私も論文試験が苦手で論文試験のある試験区分の受験をずっと後回しにしてきました。
そんな私でも、ある参考書との出会いによって苦手意識を克服してシステムアーキテクトとシステム監査技術者に独学で一発合格することができました。
この記事ではその参考書を紹介したいと思います!
こんな人にオススメ
- 論文試験が苦手・不安
- 論文試験対策として何をすればよいかわからない
- 論文試験対策のオススメの参考書が知りたい
- 論文試験対策のオススメの参考書
とてもオススメですのでぜひ見ていってください!
ズバリ、オススメの参考書はこれ!
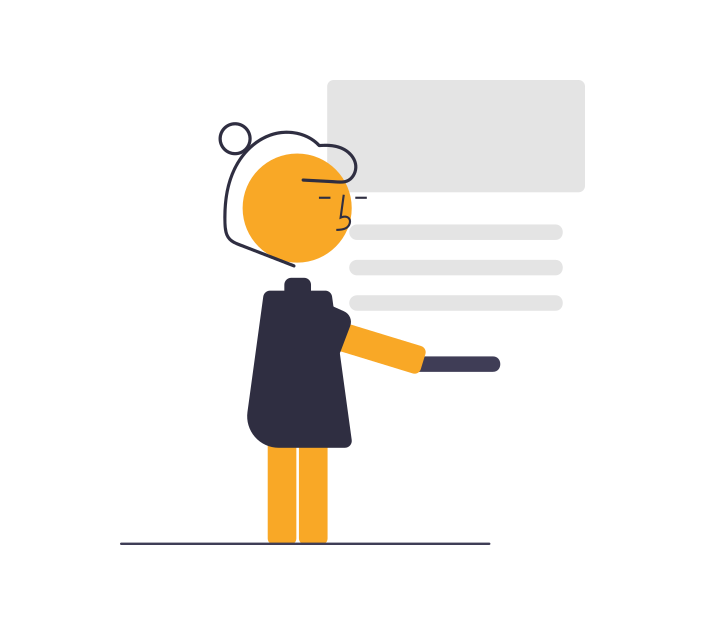
私がオススメする論文対策の参考書はズバリ「合格論文の書き方・事例集」シリーズです。
情報処理技術者試験では下記の5つの試験が論文試験の対象です。
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ITストラテジスト試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
「合格論文の書き方・事例集」シリーズは下記のように各試験の全てで対応するものが出版されています。
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ITストラテジスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験
オススメする理由
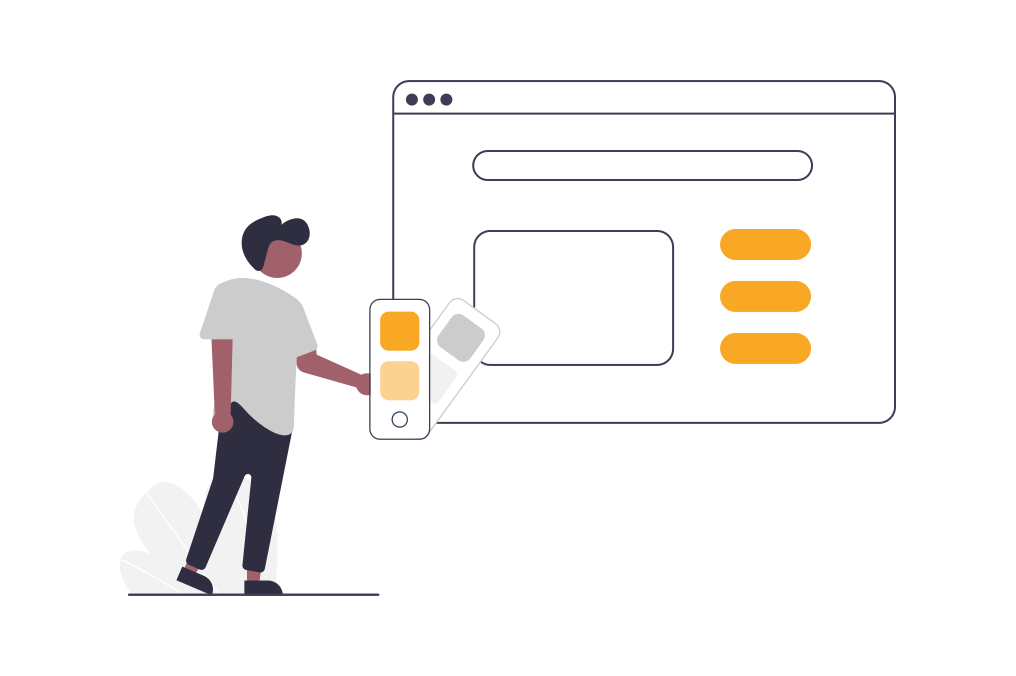
私が「合格論文の書き方・事例集」シリーズをオススメする理由をご説明します。
- 合格論文がどういう論文か具体的にわかる
- 合格論文の書き方がわかる
- 論文のネタが収集できる
合格論文がどういう論文か具体的にわかる
論文試験の難しいところはどういう論文を書いたら合格できるかが分からないところです。
「合格の書き方・事例集」シリーズでは専門家による論文事例が36本も収録されています。
論文事例を読むことで合格できる論文はどういう論文か具体的にイメージできます。
私も最初は何から手をつけたらよいか分からない状態でしたが、論文事例を何度も読むことで合格論文がどういうものかを理解することができました。
論文対策を開始する前にまずは論文事例を読んでみることをオススメします。
合格論文の書き方がわかる
合格論文がどういう論文かイメージすることができたからといって実際に論文を書けるわけではありません。
「合格の書き方・事例集」シリーズでは論文事例だけでなく合格論文の書き方についても詳しく記載されています。
私が実践して合格につながったと感じた点を2つご紹介します。
- 1.設問文を使って章立てをする
- 2.専門家としての能力をアピールする展開を盛り込む
順にご紹介します。
1.設問文を使って章立てをする
論文試験では問題文(論述すべき内容の趣旨説明)に設問文(具体的な論述すべき内容)が付属する形で出題されます。
例えば令和3年度(2021年度)春期のシステムアーキテクト試験の「問2」の設問文は下記のようになっています。
設問ア
あなたが携わった情報システムの機能追加について、対象の業務と情報システムの概要、環境の変化などの機能追加が必要になった背景、対応が求められた業務要件を、800字以内で述べよ。
設問イ
設問アで述べた機能追加において、あなたは業務要件をどのような視点でどのように分析したか。またその結果どのような設計をしたか、800字以上1600字以内で具体的に述べよ。
設問ウ
設問イで述べた機能追加における設計において、どのような目的でどのような工夫をしたか、600字以上1200字以内で具体的に述べよ。
引用元:https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2021r03_1/2021r03h_sa_pm2_qs.pdf
こちらの設問文に対して、下記のように「設問文を使って論文の章立て」をすることで、設問文に対する論述漏れを防止することができるようになります。
第1章 対象の業務と情報システムの概要、及び、機能追加が必要になった背景と対応が求められた業務要件
1.1 対象の業務
1.2 情報システムの概要
1.3 機能追加が必要になった背景
1.4 対応が求められた業務要件
第2章 業務要件の分析の視点と分析方法、及び、分析の結果採用した設計内容
2.1 業務要件の分析の視点
2.2 業務要件の分析方法
2.3 分析の結果採用した設計内容
第3章 設計において工夫した点と目的
3.1 設計において工夫した点と目的
上記はあくまで私が章立てをした例ですが設問文を箇条書きに書き直すイメージで章立てをしてもらえたら大丈夫です。
試験が開始されたら、まず初めに設問文を使って章立てをするようにしてください。
章立てをすることで論文のたたき台を作ることができ、論文の道筋ができて論理が破綻しずらくなります。
また、この作業はある程度機械的にできることなので、試験開始後まず手を動かすことで開始直後の緊張を和らげる効果もあると思います。
2.専門家としての能力をアピールする展開を盛り込む
合格論文に共通することは「専門家としての能力をアピールできている」ということです。
論文において課題を解決する展開を盛り込めば専門家としての能力をアピールできます。
具体的には下記のような展開を盛り込むことがアピールになります。
課題という困難な状況がないとアピールできないためまずは課題を示します。
○○という課題があった。
つぎに、課題に対する解決案を複数示します。
そこで私はこの課題に対する解決策として○○する案と○○する案を検討することにした。
つぎに、採用した案とその案を採用した理由を示します。
検討した結果、○○する案を採用することにした。なぜならば○○だからである。
STEP3の「採用した理由」を重点的に説明することで能力のアピールができますが、さらにダメ押しするため、 解決策を採用したことで生じる新たな課題・リスクを示します。
解決策を実施した結果、新たに○○するリスクが生じた。
さいごに、新たに生じた課題やリスクに対する解決策も示しておくことでダメ押しで能力をアピールします。
新たに生じたリスクに対して私は○○することでリスクの低減をはかった。
ここでは2つ紹介しましたが、上記以外にも様々なポイントが詳細に記載されていますのでぜひ手に取ってみてほしいです。
論文のネタが収集できる
合格論文のイメージができて合格論文の書き方が分かればあとは論文を書くだけですが、問題になるのは「論文のネタ」です。
実務経験が豊富な方はご自身の経験を論文のネタとすれば問題ありません。
実務経験がない方は論文のネタを用意する必要があります。
論文のネタ集めにもこちらの参考書はオススメです。
専門家による論文事例が36本も収録されているため、この論文事例をアレンジし論文のネタとすることができます。
もちろん論文事例をそのまま流用するのでは合格できないためアレンジが必要な点は注意してください。
また、本書では論文事例から論文のネタを収集する方法の他に「午後Ⅰ問題の問題文にある事例を使って論文を設計する方法」が説明されています。
こちらの方法も非常に有用ですのでぜひ見てほしいです。
まとめ: ズバリ「合格論文の書き方・事例集」シリーズがオススメ
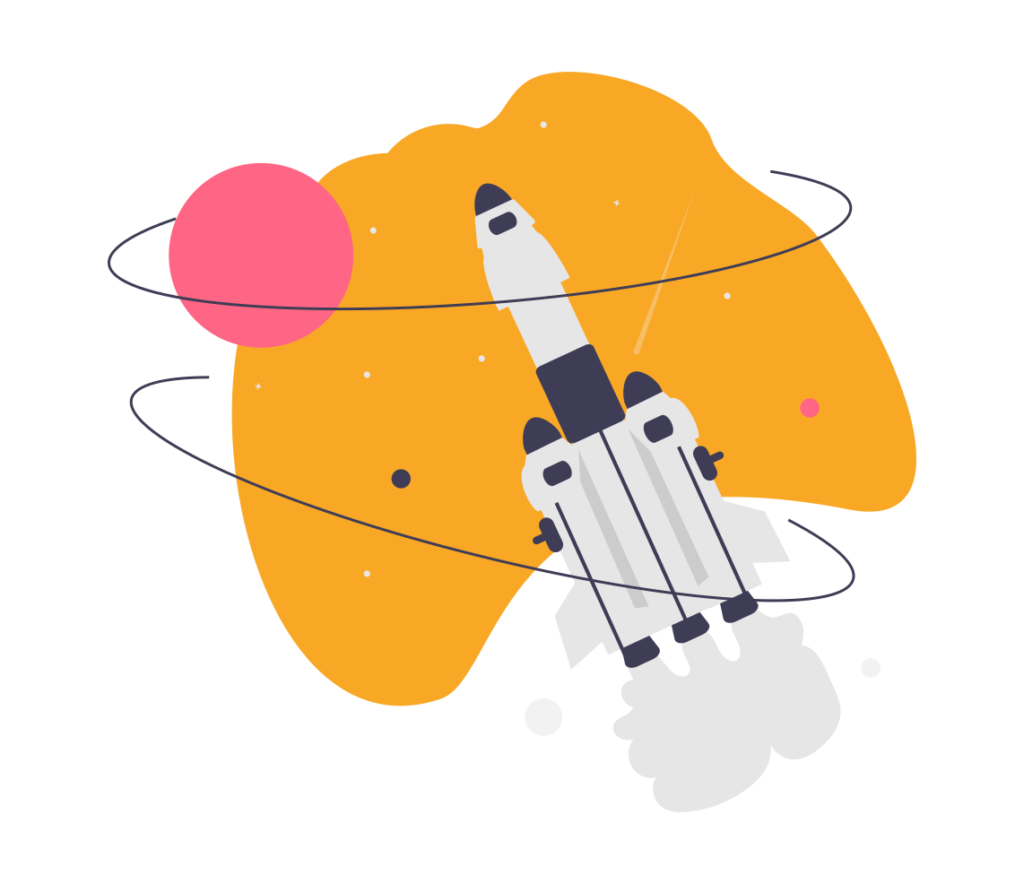
論文試験の対策は「合格論文の書き方・事例集」シリーズで事足りると私は考えています。
私が独学で「システムアーキテクト試験」「システム監査技術者試験」に一発合格できたのはこの参考書のおかげでした!
ぜひ手に取って見てみてください。
システムアーキテクト試験
プロジェクトマネージャ試験
ITストラテジスト試験
ITサービスマネージャ試験
システム監査技術者試験








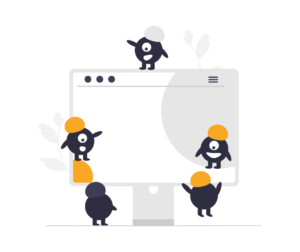
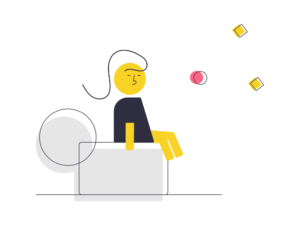
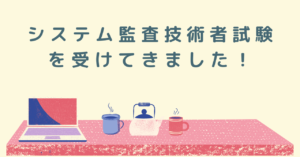
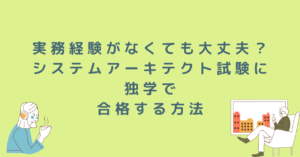

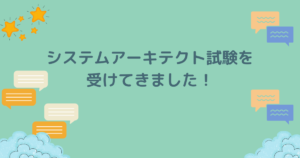

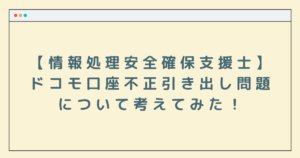
コメント